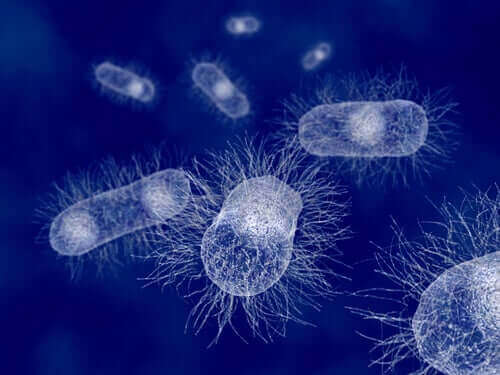ワンちゃんの耳が聞こえているかどうかを確かめる

難聴は通常シニア犬になってから起こることですが、ご家庭のワンちゃんも実はそうかもしれません。生まれつきや遺伝のためかもしれません。犬の耳が聞こえているかどうかを知るのは難しいのですが、その判断とワンちゃんのためにできることについてアドバイスをご紹介します。
犬の難聴を調べる
完全に耳が聞こえていないわけではない、というケースもあり、その場合判断がさらに難しくなります。もちろん、呼んだり話しかけても反応しなかったり、他のものへも反応を示さない場合は難聴になっている可能性があります。しかし完全に聴覚を失っていない場合は複雑です。
つまりあなたの声が聞こえるときもあればそうでないときもあるということです。またはどれくらい距離が離れているかによって、はっきりと聞こえるかどうかが変わったりします。ワンちゃんの聴覚の問題に気づくためには、観察する以上のことが必要です。ワンちゃんの注意が引けるかを試す必要があるのです。
こういったテストをするときは、なにか手の中に持てるものやワンちゃんの好きなものなどを使うといいでしょう。例えば鍵やテニスボールなどです。ワンちゃんがリラックスしているときに気づかれないようにワンちゃんに近づき、鍵をじゃらじゃら鳴らして反応するかどうか調べてみましょう。

ワンちゃんが寝ているときに手を耳元で叩いて反応するかをみることもできます。音が鳴るおもちゃや何かを床に落とすことでも反応を調べることができます。
獣医さんへの相談
こういったテストをしてみて、ワンちゃんの聴覚に問題があるのではということに気が付いたら、獣医さんに連れていきましょう。すると、BAER検査(聴性脳幹誘発反応検査)を行ってくれます。この検査をすると、犬の脳が音に反応する様子を調べることができるのです。
検査は犬の頭と耳に電極を付けて行われます。これにより、犬に聴覚の問題があるかどうかだけでなく、それがどのくらいの程度で、どの分野に問題があるのかを知ることができます。
また、どれくらいの音が犬の耳に届いていて、微細なものでも反応があるかどうかもわかります。他にも獣医さんで使われる検査はありますが、BAER検査ほど正確なものはありません。しかし、専門家の中には代わりに歪成分耳音響放射(DPOAE)や自動耳音響放射(OAE)、うずまき管マイクを使う人もいます。
こういった検査も犬の難聴を診断するのに利用できます。しかし、どの程度の難聴なのか、またどの部位が影響を受けているのかを調べることはできません。あまりたくさんの詳細はわからないとはいえ、この診断もとても信頼できるものです。

犬の難聴の最もよくある原因
犬に難聴が起こるのにはいくつかの原因があります。すでに述べたように、犬が若い場合には先天的なもの、遺伝的なもの、そしてなんらかの外相の結果の可能性もあります。老犬については、以下のような要因があります。
- 分泌物のある耳炎
- 慢性的な耳炎によって外耳道が狭まること
- 鼓膜の破裂
- 骨の変性
耳炎のケアがきちんとできていなかったり、加齢によって骨量が減少したりすると、犬の耳が全く聞こえなくなってしまうかもしれません。これについてなにかできることはあるのでしょうか。実は、自分たちが歳をとって起こる影響を止められないのと同じように、あまりできることはないのです。
それでも、耳炎がその他の感染症が起こって聴覚を失うことがないように、耳掃除をしてあげましょう。一生を通してサプリを定期的にあげたりすることでも、ワンちゃんの骨を強くすることができますが、ワンちゃんの加齢がどの程度の影響をもたらすのかは時間が経たないとわかりません。
ワンちゃんの難聴は意外によくあることです。あなたのワンちゃんにも起こる前に、それを予防できる手段をとりましょう!
難聴は通常シニア犬になってから起こることですが、ご家庭のワンちゃんも実はそうかもしれません。生まれつきや遺伝のためかもしれません。犬の耳が聞こえているかどうかを知るのは難しいのですが、その判断とワンちゃんのためにできることについてアドバイスをご紹介します。
犬の難聴を調べる
完全に耳が聞こえていないわけではない、というケースもあり、その場合判断がさらに難しくなります。もちろん、呼んだり話しかけても反応しなかったり、他のものへも反応を示さない場合は難聴になっている可能性があります。しかし完全に聴覚を失っていない場合は複雑です。
つまりあなたの声が聞こえるときもあればそうでないときもあるということです。またはどれくらい距離が離れているかによって、はっきりと聞こえるかどうかが変わったりします。ワンちゃんの聴覚の問題に気づくためには、観察する以上のことが必要です。ワンちゃんの注意が引けるかを試す必要があるのです。
こういったテストをするときは、なにか手の中に持てるものやワンちゃんの好きなものなどを使うといいでしょう。例えば鍵やテニスボールなどです。ワンちゃんがリラックスしているときに気づかれないようにワンちゃんに近づき、鍵をじゃらじゃら鳴らして反応するかどうか調べてみましょう。

ワンちゃんが寝ているときに手を耳元で叩いて反応するかをみることもできます。音が鳴るおもちゃや何かを床に落とすことでも反応を調べることができます。
獣医さんへの相談
こういったテストをしてみて、ワンちゃんの聴覚に問題があるのではということに気が付いたら、獣医さんに連れていきましょう。すると、BAER検査(聴性脳幹誘発反応検査)を行ってくれます。この検査をすると、犬の脳が音に反応する様子を調べることができるのです。
検査は犬の頭と耳に電極を付けて行われます。これにより、犬に聴覚の問題があるかどうかだけでなく、それがどのくらいの程度で、どの分野に問題があるのかを知ることができます。
また、どれくらいの音が犬の耳に届いていて、微細なものでも反応があるかどうかもわかります。他にも獣医さんで使われる検査はありますが、BAER検査ほど正確なものはありません。しかし、専門家の中には代わりに歪成分耳音響放射(DPOAE)や自動耳音響放射(OAE)、うずまき管マイクを使う人もいます。
こういった検査も犬の難聴を診断するのに利用できます。しかし、どの程度の難聴なのか、またどの部位が影響を受けているのかを調べることはできません。あまりたくさんの詳細はわからないとはいえ、この診断もとても信頼できるものです。

犬の難聴の最もよくある原因
犬に難聴が起こるのにはいくつかの原因があります。すでに述べたように、犬が若い場合には先天的なもの、遺伝的なもの、そしてなんらかの外相の結果の可能性もあります。老犬については、以下のような要因があります。
- 分泌物のある耳炎
- 慢性的な耳炎によって外耳道が狭まること
- 鼓膜の破裂
- 骨の変性
耳炎のケアがきちんとできていなかったり、加齢によって骨量が減少したりすると、犬の耳が全く聞こえなくなってしまうかもしれません。これについてなにかできることはあるのでしょうか。実は、自分たちが歳をとって起こる影響を止められないのと同じように、あまりできることはないのです。
それでも、耳炎がその他の感染症が起こって聴覚を失うことがないように、耳掃除をしてあげましょう。一生を通してサプリを定期的にあげたりすることでも、ワンちゃんの骨を強くすることができますが、ワンちゃんの加齢がどの程度の影響をもたらすのかは時間が経たないとわかりません。
ワンちゃんの難聴は意外によくあることです。あなたのワンちゃんにも起こる前に、それを予防できる手段をとりましょう!
このテキストは情報提供のみを目的としており、専門家との相談を代替するものではありません。疑問がある場合は、専門家に相談してください。